MENU
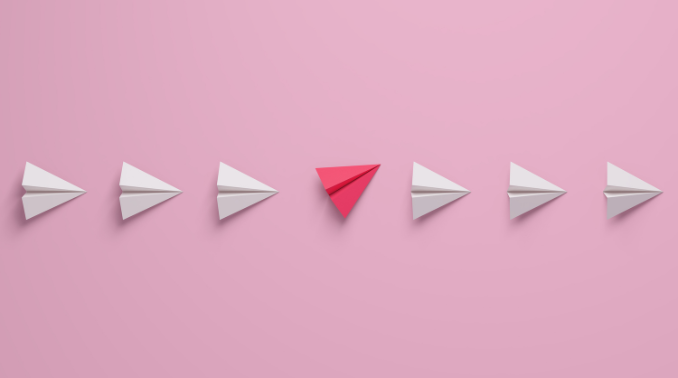
〇保険会社が提供している「代理店向けオンライン」の操作性が悪い
〇鉄道会社が提供している「お客様向けチケット購入ネット」が使いにくい
一方で、コンビニ店舗の端末では、入社したばかりの店員がすぐに、物品販売、宅配便、チケット販売、すべてをミスなくこなしてしまう操作性になっている
事象として「操作性が悪い」という問題が見えているが、果たして、原因はそのシステム作りにあるのだろうか。
対処の方策は二つあって、システムの問題だからSEに改善を指示するという方策と、見えていない本質的な真の問題が別にあるのではないかと問いを立て、真の問題を深く掘りあてていく方策とある。
デジタルは、ビジネスの現場を写す鏡のような性質がある。従って、デジタルでの問題を深掘りしていくと、可視化しにくいビジネス現場の問題を探し出すことにつながり、それが「真の問題」ということが多い。
デジタルで表面化した問題、例えば、使いにくい、使われていない、かえって煩雑になった、などは、実はビジネスが持っている問題の症状だと認識すべきなのだ。そこをデジタル部門が強く主張すべきだし、経営もそれを学ばなければいけない。
代理店オンラインの操作性の例で真の問題を掘り当てるプロセスを考えてみよう。
上記のヒアリングの内容を、「ステークホルダー間の関係性」や「発言の背後にある構造や文脈」を意識して、構造的な問題を見極めていく。具体的に見えていない問題が隠れているので、関係者からの言い分だけでは、問題ははっきりしない。また、「しっかりやる」とか「緊張感がない」とかという精神論では解決しないので、あくまで、科学的に分析する。
例えば、真の問題は「保険商品の約款や規定が複雑すぎて、人が理解する範囲を超えている」という仮説を立て、関係者と仮説が正しいかどうかを議論する。各ステークホルダーの意見には、それぞれの前提や条件があってのことなので、そこをできるだけオープンに可視化することで本質的な議論を行うことができる。
それぞれの縦割り部門にはそれまでの歴史や哲学があるので、納得できる成案をつくるには、猛烈な議論が想定される。野中教授は、「知的コンバット」からイノベーションが生まれると説いているが、まさに、コンバットが繰り返されるだろう。そのなかで、成案を導き出す力がその企業に必要だ。
上に書いた検討プロセスを必要とする課題は、他にも存在する。
例えば、「新商品開発を社内の多くの部門のノウハウを融合させて進めたい」とか、「顧客目線で自社のネットサービスを統合化されたものにしたい」とか、「基幹系システムの再構築にあたり、全体最適な視点からビジネスプロセスを見直したい」など、いろいろある。
これらに共通するのは、企業における大きな二つの課題だ。
① 一つの縦割り部門だけでは、真の問題を深掘りすることはできない
② 表面に現れた事象から、本質的な全社的課題を見極めて、真の課題に昇華し、その解決策を検討・実行することができる部門が存在しない
現状の企業の活動の中には、このような機能を有する部門や人材はいない。そこを改革していかないと、全社的なDXなどできるわけがない。
各縦割り部門を適切にファシリテートするには、どの縦割りにも所属しない中立な部門が必要だ。そして、その部門に縦割り部門に指示できる権限を付与することが必要だろう。単なるアドバイスでは縦割り部門は動かない。
もっと大事なのは、誰がその役割を果たせるか、という人材問題だ。3.に書いたプロセスを実践できる人が社内にいるかという問題だ。
社外の代理店にヒアリングできる人、別の部門にうかがってその部門の主張を正確に認知できる人、役員と対峙して適切な質問をしながらその意図を理解できる人、課題を抽象化し、構造的に分析できる人、多くの関係者の意見を集約して納得できそうな成案を作成できる人、そのような人がいるといいのだが、そんなスーパーマンは普通いない。
とすると、そういう人材を育成する意味を含めて、日常的にそのような仕事をする部門を活動させておくことが必要だろう。その実際の業務をしている中で、不足している能力や学ぶべきスキルに気づき、それを必死に取得に行くという姿勢が必要なのではないだろうか。
ヨコグシ部門と問題を掘り当てることができる人材の両方を準備しないと、「真の問題探しジャーニー」は実行できない。
世界の多くの国で、20年も前から、ヨコグシの「プロセスオフィス」を本社機能に置き、事業部門に指示を出す権限を持たせ、「ビジネスアナリスト(BA)」という専門性を磨いた人材を配置し、実践している。
そういう世界の企業と戦って、今の体制の日本企業が生き残れるのだろうか。重大な経営課題だと私は思う。
他のDBIC活動
他のDBICコラム
他のDBICケーススタディ

【レポート】2025年12月 DBICアップデート

【レポート】自分の「感覚」に再び出会う旅。DBIC デジタル・ストーリーテリング(DST)ワークショップを開催

【レポート】UNLOCK QUEST2025上期レポート 問いを立てて行動し続けること

【レポート】2025年9月 DBICアップデート 恵比寿から高輪「LX Hub」へ ― DBICの第4の変革
一覧へ戻る
一覧へ戻る
一覧へ戻る

