MENU
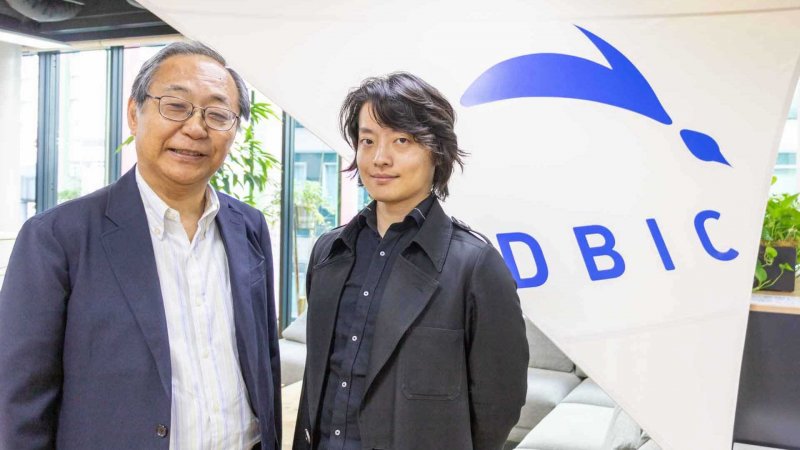
スピーカーは株式会社オリィ研究所代表取締役CEOの吉藤オリィ様。同社は分身ロボット「OriHime」や、眼球移動によるPC操作システム「OriHime eye」といった革新的な製品により、ALSなどの疾病や事故により肢体が不自由となった皆様のQOL向上や雇用を実現し、大きな注目を集めています。 本講演では、吉藤様が分身ロボット開発に取り組むに至るまでの原体験、ロボットカフェなど近年の成果、そして本質的な目標である「孤独の解消」そして「役割」をテーマにお話しいただきました。また、記事の後半では一般社団法人SORAのかけはし代表理事の仲佐昭彦様による「オリヒメスペースフライトプロジェクト」の紹介も掲載しています。なお、本レポートでは講演内容を再構成してお伝えします。  吉藤オリィ様。写真右下に見えるのが分身ロボットOriHime
吉藤オリィ様。写真右下に見えるのが分身ロボットOriHime
吉藤:私は小さな頃から身体が弱く、小学校5年生から体調不良のストレス性の腹痛などが原因で、3年半ほど不登校でした。引きこもり状態。うつに近い状態です。 でも世間から見たら「ズル休み」「怠けている」という扱いを受けてしまいます。それは強い孤独を生んで「自分は誰からも必要とされていない。社会の荷物なんだ」という気持ちになりました。  引きこもり中に2週間、誰とも話さず寝たきりで天井ばかり見ていると、ふと日本語がうまく口から出なくなっていることに気づきました。笑うための筋肉の使い方も忘れてしまって、不自然な笑顔しかつくれなくなってしまうのです。 たった2週間でこうなってしまうのですから、生まれつき障害を持っていたり、長く病気を患っている皆さんは、どれほどの思いで暮らしているのか。これをどうやって解消していくか、というテーマが最終的にはOriHimeの開発につながっていきます。
引きこもり中に2週間、誰とも話さず寝たきりで天井ばかり見ていると、ふと日本語がうまく口から出なくなっていることに気づきました。笑うための筋肉の使い方も忘れてしまって、不自然な笑顔しかつくれなくなってしまうのです。 たった2週間でこうなってしまうのですから、生まれつき障害を持っていたり、長く病気を患っている皆さんは、どれほどの思いで暮らしているのか。これをどうやって解消していくか、というテーマが最終的にはOriHimeの開発につながっていきます。
 吉藤:私が不登校から社会復帰できたきっかけは、ロボット大会への出場でした。子供の頃から折り紙が好きだった私を見ていた母が、私にロボットづくりを勧めてくれたのです。 中学2年生のとき、地区大会では偶然の助けもあって優勝することができました。全国大会ではそうはいかないと思ってプログラミングなどを改善し、準優勝。そこで初めて「がんばると報われる」とか「一位になれなかったのが悔しい」という感情を知りました。 私は奈良の出身で、奈良には「奈良のエジソン」と呼ばれる久保田憲司先生がいらっしゃいます。まだセグウェイもない時代に、一輪車が自立走行するクッピーというロボットをつくっているのを見て、「この先生はすごい。弟子入りしたい」と強く思い、先生が教えている工業高校に進学しました。学校に行く目的ができたのです。 当時から福祉機器に興味があって、高校の3年間は半田ゴテを握りながら車椅子の開発に没頭しました。奈良は坂が多いので、当時まだ高価だったジャイロセンサーを搭載し、どんな坂道でも傾かない機構を搭載しました。 更には段差が登れるタイヤホイールを発明し、論文を書いたところ、アメリカで開催されたインテル国際学生科学技術フェア(ISEF)のエンジニアリング部門で世界3位を頂くことができました。高校3年生のときです。
吉藤:私が不登校から社会復帰できたきっかけは、ロボット大会への出場でした。子供の頃から折り紙が好きだった私を見ていた母が、私にロボットづくりを勧めてくれたのです。 中学2年生のとき、地区大会では偶然の助けもあって優勝することができました。全国大会ではそうはいかないと思ってプログラミングなどを改善し、準優勝。そこで初めて「がんばると報われる」とか「一位になれなかったのが悔しい」という感情を知りました。 私は奈良の出身で、奈良には「奈良のエジソン」と呼ばれる久保田憲司先生がいらっしゃいます。まだセグウェイもない時代に、一輪車が自立走行するクッピーというロボットをつくっているのを見て、「この先生はすごい。弟子入りしたい」と強く思い、先生が教えている工業高校に進学しました。学校に行く目的ができたのです。 当時から福祉機器に興味があって、高校の3年間は半田ゴテを握りながら車椅子の開発に没頭しました。奈良は坂が多いので、当時まだ高価だったジャイロセンサーを搭載し、どんな坂道でも傾かない機構を搭載しました。 更には段差が登れるタイヤホイールを発明し、論文を書いたところ、アメリカで開催されたインテル国際学生科学技術フェア(ISEF)のエンジニアリング部門で世界3位を頂くことができました。高校3年生のときです。
 吉藤:その大会で、世界の高校生と交流したのが、人生の大きな転機になりました。彼らの多くは「自分がやっている研究は、自分の人生そのものだ。自分はこの研究をするために生まれてきて、この研究をしながら死にたい」と大真面目に語るのです。実際に彼らは博識で、物理であれ宇宙であれ、自分の専門分野だったら24時間でも話し続けられるような人たちでした。 そんな言葉は、日本で競った高校生からは一度も聞かなかったし、自分でも考えたことはありませんでした。そこで「自分は本当に、車椅子を一生つくり続けたいのか?」「自分が本当にしたいことはなんなのか?」と考えながら帰国することになります。 奈良に戻ると、「世界3位の賞を取ったスーパー高校生」という扱いで、メディアに多く取り上げていただいた結果、各方面からものづくりの相談がくるようになりました。
吉藤:その大会で、世界の高校生と交流したのが、人生の大きな転機になりました。彼らの多くは「自分がやっている研究は、自分の人生そのものだ。自分はこの研究をするために生まれてきて、この研究をしながら死にたい」と大真面目に語るのです。実際に彼らは博識で、物理であれ宇宙であれ、自分の専門分野だったら24時間でも話し続けられるような人たちでした。 そんな言葉は、日本で競った高校生からは一度も聞かなかったし、自分でも考えたことはありませんでした。そこで「自分は本当に、車椅子を一生つくり続けたいのか?」「自分が本当にしたいことはなんなのか?」と考えながら帰国することになります。 奈良に戻ると、「世界3位の賞を取ったスーパー高校生」という扱いで、メディアに多く取り上げていただいた結果、各方面からものづくりの相談がくるようになりました。
 吉藤:今でも忘れられないのは、広島にいるおばあさんからかかってきた電話です。「吉藤さん、あなたのつくった車椅子はすごくかっこいいけど、私は要らない。私はあなたにローラーが付いた座布団をつくってほしい」と言うのです。 よくよく聞いてみると、おばあさんは足腰が弱って立ち上がることができず、朝起きると座布団の上に座って、同居している娘さんが座布団ごとおばあさんを引っ張って家の中を移動しているとのことでした。その娘さんも50歳を過ぎて腰が悪くなってきたから、娘さんが座布団を簡単に引っ張れるように、ローラー付きの座布団がほしいというわけです。 この話を聞いて私はふたつのショックを受けました。ひとつは、どうしてそれを高校生の私に頼んできたのか、という点です。広島だったら大きな企業もたくさんあるから、そういうところに頼んだらいいじゃないかと。そうしたら、おばあさんは「もう電話はした。でも何の相手もしてもらえなかった」と。 ふたつめは、私は、足腰が悪い人が実際にどんな思いで毎日暮らしているかを全く知らずに車椅子の開発をしていた、という点です。私にとっては車椅子の研究は、世間の荷物だと思っていた自分が誰かの役に立つための生きがいでした。でも、論文で世界3位の賞を取っても、現場に足を運んでいなかったのです。
吉藤:今でも忘れられないのは、広島にいるおばあさんからかかってきた電話です。「吉藤さん、あなたのつくった車椅子はすごくかっこいいけど、私は要らない。私はあなたにローラーが付いた座布団をつくってほしい」と言うのです。 よくよく聞いてみると、おばあさんは足腰が弱って立ち上がることができず、朝起きると座布団の上に座って、同居している娘さんが座布団ごとおばあさんを引っ張って家の中を移動しているとのことでした。その娘さんも50歳を過ぎて腰が悪くなってきたから、娘さんが座布団を簡単に引っ張れるように、ローラー付きの座布団がほしいというわけです。 この話を聞いて私はふたつのショックを受けました。ひとつは、どうしてそれを高校生の私に頼んできたのか、という点です。広島だったら大きな企業もたくさんあるから、そういうところに頼んだらいいじゃないかと。そうしたら、おばあさんは「もう電話はした。でも何の相手もしてもらえなかった」と。 ふたつめは、私は、足腰が悪い人が実際にどんな思いで毎日暮らしているかを全く知らずに車椅子の開発をしていた、という点です。私にとっては車椅子の研究は、世間の荷物だと思っていた自分が誰かの役に立つための生きがいでした。でも、論文で世界3位の賞を取っても、現場に足を運んでいなかったのです。
吉藤:それまでの私はずっと、日本の社会はよくできていて、それに適合できない自分が間違っていると思っていました。でも、そのおばあさんが高校生に電話をしてこなければいけない社会は間違っている、と思い直しました。高校を出たら、奈良県の町工場で車椅子職人になろうと考えていたのですが、そういった当事者からの相談をたくさん受けるうちに、研究者の道に進もうと決心しました。 手が動かない目が見えない、という不自由と同じだけ、もしくはそれ以上に、それによって家族の介護を受け続けなければならない「申し訳ない」「自分がいないほうが家族は幸せなんじゃないか」という孤独感が深刻だったのです。 自分にも思い当たることがありました。私が引きこもりだった頃、妹は家族旅行に行くことができなかった。そのとき「自分は家族の荷物」だという自覚がありました。この問題だけは絶対に解決しなければならない、と思いました。
 吉藤:最初は高専で人工知能を使った友達ロボット開発に取り組んだのですが、すぐに「人工知能で人は癒せない」という結論に至りました。学校に行けない人が学校に行けるようになる、ということを「癒やす」と定義するなら、人を癒せるのは人しかいないのです。 車椅子の研究をしたのも「移動」をサポートするためだったのですが、それでは車椅子さえ使うことができない、病院または家から出られない人を救うことができない。 初期のOriHimeは、私が早稲田大学に在学中に、学友が入院して学校に来られなくなったときに開発しました。カメラとマイクとスピーカーを内蔵したロボットを教室に置いておけば、教授が話している内容が聞こえて、黒板が見えて、手を上げて先生に質問するこができたのです。 それに「分身ロボット」というカテゴリーを名付けて、今日まで研究を続けています。これが、引きこもりだったときの自分が欲しかったものでした。これがあれば、学校にも、遠足にも行けたかも知れない。思い出がつくれたかもしれない。
吉藤:最初は高専で人工知能を使った友達ロボット開発に取り組んだのですが、すぐに「人工知能で人は癒せない」という結論に至りました。学校に行けない人が学校に行けるようになる、ということを「癒やす」と定義するなら、人を癒せるのは人しかいないのです。 車椅子の研究をしたのも「移動」をサポートするためだったのですが、それでは車椅子さえ使うことができない、病院または家から出られない人を救うことができない。 初期のOriHimeは、私が早稲田大学に在学中に、学友が入院して学校に来られなくなったときに開発しました。カメラとマイクとスピーカーを内蔵したロボットを教室に置いておけば、教授が話している内容が聞こえて、黒板が見えて、手を上げて先生に質問するこができたのです。 それに「分身ロボット」というカテゴリーを名付けて、今日まで研究を続けています。これが、引きこもりだったときの自分が欲しかったものでした。これがあれば、学校にも、遠足にも行けたかも知れない。思い出がつくれたかもしれない。
 吉藤:私の会社、オリィ研究所では、3年ほど前から、分身ロボットが働いています。(編集注:動画を上映)今、見ていただいたのは、番田裕太という私の友人でもある社員が、盛岡から遠隔操作でOriHimeを使って勤務している様子でした。番田は4歳のときに交通事故で脊椎損傷を受け、そこから20年以上寝たきりの状態でした。 そんな彼と一緒にOriHimeの改良を続け、彼はそのうちオリィ研究所にとって不可欠な人材になっていました。私が講演するときも、いつも横に居て、頷いたり、ときにはマイクを渡して話してもらうこともできました。講演後に、来場者と挨拶したり、雑談したり、人と出会うことだってできます。番田が東京に来れば、講演で知り合った皆さんが集まってパーティが開催されました。 これまでの社会は身体至上主義でした。よく「身体が資本」と言いますが、それでは身体が動かなければ資本はないのでしょうか。番田はフロントランナーとして、テクノロジーを使えばここまでできる、ということを示し続けてくれました。残念ながら、1年半ほど前に、内臓の機能が失われて彼は28歳で息を引き取りました。 番田は4歳で事故にあって、特別支援学校さえ行けなかったのです。その番田が24歳から顎の筋肉を使ってメールを打つことを始めて、6,000通のメールを送った中で私と出会うことができました。彼は「誰かの役に立ちたい」と強く望んでいました。 最初はテキストチャットを使ってテレワークで働いてもらおうとしました。でもこれだと、オフィスの誰かが「敢えて番田のために仕事を切り出す」という負荷を感じてしまい機能しませんでした。そこで、OriHimeに切り替えて、朝の9時から夕方5時まで「出社」してもらうスタイルに切り替えました。 そうすると、誰が忙しくしているか空気感が伝わるようになって、自分から「それ、俺がやります」と言い始めたのです。ランチや雑談もオフィスのみんなとしていると、帰属意識も芽生えてきました。
吉藤:私の会社、オリィ研究所では、3年ほど前から、分身ロボットが働いています。(編集注:動画を上映)今、見ていただいたのは、番田裕太という私の友人でもある社員が、盛岡から遠隔操作でOriHimeを使って勤務している様子でした。番田は4歳のときに交通事故で脊椎損傷を受け、そこから20年以上寝たきりの状態でした。 そんな彼と一緒にOriHimeの改良を続け、彼はそのうちオリィ研究所にとって不可欠な人材になっていました。私が講演するときも、いつも横に居て、頷いたり、ときにはマイクを渡して話してもらうこともできました。講演後に、来場者と挨拶したり、雑談したり、人と出会うことだってできます。番田が東京に来れば、講演で知り合った皆さんが集まってパーティが開催されました。 これまでの社会は身体至上主義でした。よく「身体が資本」と言いますが、それでは身体が動かなければ資本はないのでしょうか。番田はフロントランナーとして、テクノロジーを使えばここまでできる、ということを示し続けてくれました。残念ながら、1年半ほど前に、内臓の機能が失われて彼は28歳で息を引き取りました。 番田は4歳で事故にあって、特別支援学校さえ行けなかったのです。その番田が24歳から顎の筋肉を使ってメールを打つことを始めて、6,000通のメールを送った中で私と出会うことができました。彼は「誰かの役に立ちたい」と強く望んでいました。 最初はテキストチャットを使ってテレワークで働いてもらおうとしました。でもこれだと、オフィスの誰かが「敢えて番田のために仕事を切り出す」という負荷を感じてしまい機能しませんでした。そこで、OriHimeに切り替えて、朝の9時から夕方5時まで「出社」してもらうスタイルに切り替えました。 そうすると、誰が忙しくしているか空気感が伝わるようになって、自分から「それ、俺がやります」と言い始めたのです。ランチや雑談もオフィスのみんなとしていると、帰属意識も芽生えてきました。
 DBIC代表 横塚裕志 吉藤:平成27年の文科省のデータでは、重度肢体不自由児の特別支援学校は日本国内に345校、重度肢体不自由児童は約36,000人います。平成29年3月に特別支援学校を卒業した生徒のうち、知的障害者の就職率は3割ほどありますが、肢体不自由者は5%程度です。 ほとんどの肢体不自由者は、卒業後も施設に入所します。1970年代からの障害者就職率の遷移を見ても、全体としては上がっているのですが、肢体不自由者は減少傾向にあります。 しかし、番田の活躍がテレビで放送されたこともあり、多くの人が「番田に続け」と新しい働き方を模索し始めました。様々な企業様とのパートナーシップも生まれています。これまでのテレワークのように、作業をもらって成果を送り返すスタイルでは、お金は稼げるかもしれませんが、帰属意識は生まれないのです。 私も不登校の時期に、学校から宿題だけ送られてきても、それを解こうという気持ちがどんどんなくなりました。重要なのは休み時間に友達と遊んだり、文化祭に参加したりすることなのです。OriHimeを使うことで、4年間不登校だった子供が学校に戻れたケースがあります。
DBIC代表 横塚裕志 吉藤:平成27年の文科省のデータでは、重度肢体不自由児の特別支援学校は日本国内に345校、重度肢体不自由児童は約36,000人います。平成29年3月に特別支援学校を卒業した生徒のうち、知的障害者の就職率は3割ほどありますが、肢体不自由者は5%程度です。 ほとんどの肢体不自由者は、卒業後も施設に入所します。1970年代からの障害者就職率の遷移を見ても、全体としては上がっているのですが、肢体不自由者は減少傾向にあります。 しかし、番田の活躍がテレビで放送されたこともあり、多くの人が「番田に続け」と新しい働き方を模索し始めました。様々な企業様とのパートナーシップも生まれています。これまでのテレワークのように、作業をもらって成果を送り返すスタイルでは、お金は稼げるかもしれませんが、帰属意識は生まれないのです。 私も不登校の時期に、学校から宿題だけ送られてきても、それを解こうという気持ちがどんどんなくなりました。重要なのは休み時間に友達と遊んだり、文化祭に参加したりすることなのです。OriHimeを使うことで、4年間不登校だった子供が学校に戻れたケースがあります。
 吉藤:Jリーグとも提携して現場での観戦をOriHimeで体験したり、松岡修造さんとテニスをしたり、横浜の音楽祭ではOriHimeで参加するのとセットで、ライターとしての仕事を受託する試みもしています。最近ニーズが多いのは、結婚式へのOriHime参加です。 アメリカ在住でどうしても日本の結婚式に来られなかった人がOriHimeで披露宴に出たのですが、本人の声が聞こえて会話ができますから、新郎新婦からすると「忙しいのに来てくださった」という気持ちになっていました。両者に「来てくれた」「行った」という共通認識が芽生えたなら、これはもう「行った」と扱って差し支えないのではないでしょうか。 新聞やテレビでも報道もされた、OriHimeで卒業式に参加した教頭先生のエピソードがあります。58歳でALSを発症し、それまで勤め上げてきた学校を辞めざるを得なくなったのです。秋から学校に行くこともできなくなったのですが、生徒会がぜひ卒業式に出てほしいと要望して、OriHimeで参加することができました。 教頭先生はALSであることがわかったとき「これから先、他人にお願いして生かされるくらいなら死んだほうがいい」と明確におっしゃっていました。ところが、卒業式を終えると「まだ自分にはできることがある。まだ子どもたちに伝えたいことがある」と気持ちが変わり、呼吸器をつけて延命することを選択されました。今ではALS協会の広島部会の副支部長に就任し、講演活動をされています。 ALSに限った話ではありませんが、人間は辛くなったとき「死なない理由」を探すことになるのです。その理由が見つかった人は呼吸器をつけて延命し、見つけられなかった人は呼吸器をつけずに尊厳死を選びます。ALSの患者は日本に約1万人。そのうち呼吸器をつける人は3,000人も居なくて、7割の人は呼吸器をつけない選択をしています。 いつ、誰が発症してもおかしくない病気です。生きる道を選んだとしても、最終的には眼球しか動かせなくなります。何を目的に生きるのか。私は最初、「移動」や「出会い」が重要だと思っていました。しかし、番田が言っていたように、本当に重要なのは「どうやって誰かの役に立てるか」という「役割」なのです。
吉藤:Jリーグとも提携して現場での観戦をOriHimeで体験したり、松岡修造さんとテニスをしたり、横浜の音楽祭ではOriHimeで参加するのとセットで、ライターとしての仕事を受託する試みもしています。最近ニーズが多いのは、結婚式へのOriHime参加です。 アメリカ在住でどうしても日本の結婚式に来られなかった人がOriHimeで披露宴に出たのですが、本人の声が聞こえて会話ができますから、新郎新婦からすると「忙しいのに来てくださった」という気持ちになっていました。両者に「来てくれた」「行った」という共通認識が芽生えたなら、これはもう「行った」と扱って差し支えないのではないでしょうか。 新聞やテレビでも報道もされた、OriHimeで卒業式に参加した教頭先生のエピソードがあります。58歳でALSを発症し、それまで勤め上げてきた学校を辞めざるを得なくなったのです。秋から学校に行くこともできなくなったのですが、生徒会がぜひ卒業式に出てほしいと要望して、OriHimeで参加することができました。 教頭先生はALSであることがわかったとき「これから先、他人にお願いして生かされるくらいなら死んだほうがいい」と明確におっしゃっていました。ところが、卒業式を終えると「まだ自分にはできることがある。まだ子どもたちに伝えたいことがある」と気持ちが変わり、呼吸器をつけて延命することを選択されました。今ではALS協会の広島部会の副支部長に就任し、講演活動をされています。 ALSに限った話ではありませんが、人間は辛くなったとき「死なない理由」を探すことになるのです。その理由が見つかった人は呼吸器をつけて延命し、見つけられなかった人は呼吸器をつけずに尊厳死を選びます。ALSの患者は日本に約1万人。そのうち呼吸器をつける人は3,000人も居なくて、7割の人は呼吸器をつけない選択をしています。 いつ、誰が発症してもおかしくない病気です。生きる道を選んだとしても、最終的には眼球しか動かせなくなります。何を目的に生きるのか。私は最初、「移動」や「出会い」が重要だと思っていました。しかし、番田が言っていたように、本当に重要なのは「どうやって誰かの役に立てるか」という「役割」なのです。
 吉藤:オリィ研究所も、肢体不自由者が「仕事ができる」機会や環境をつくることに向かって徐々にシフトしていきました。企業の中ではNTT東日本さんが、いちばん多くOriHimeを導入してくださっています。 女性社員が産休、育休で数年間休んだ後、職場復帰がしづらくて辞めてしまうケースが多かったのですが、OriHimeを使って家に居ながら1時間でも2時間でも「出社」することで、同僚と関係性が維持できて、「仕事をしている」という実感が得られるのです。現時点で66台導入してくださっています。 国会議員の平将明さんもOriHimeで国会に出てみようと言ってくださっています。OriHimeを肢体不自由者だけが使うものではなく、誰もが使えるインフラにしてしまえばいいのです。国会議員が使っていたら、学校で使えない理由なんてありませんよね。 これまでは万能人材社会でした。日本だと政治家にも車椅子の人はなかなかいません。身体が不自由な人は上に立てなかった。でも、実際にはとても優秀でキャリアもある人材が、ある日ALSを発症してしゃべれなくなり、それで就職できなくなってしまっているケースも多くあります。 オリィ研究所のもうひとつの商品、「OriHime eye」は、視線移動だけで文字入力はもちろん、Windows PCのすべての操作が可能になっています。定価45万円ですが、ALSや筋ジストロフィーの患者さんが購入補助を使えば4万5,000円で導入できます。 ビジネス経験のない自分がここまでやってこれたのは、メンターの存在がありました。メリルリンチ証券の元会長の藤沢さんという方で、ALSを発症して10年間寝たきりだったところ、初期段階のOriHime eyeを購入してくださったユーザーさんです。残念ながら亡くなってしまいましたが、最後の瞬間までオリィ研究所の顧問を務めてくださいました。エンジェル投資家でもありました。 がんも患っていらっしゃったのに「20代の若者とベンチャーができるなんて楽しい」とずっと言ってくださった。私も、将来寝たきりになったとしても、若者たちとプロジェクトをやりたいです。それが藤沢さんの生き様から学んだことです。
吉藤:オリィ研究所も、肢体不自由者が「仕事ができる」機会や環境をつくることに向かって徐々にシフトしていきました。企業の中ではNTT東日本さんが、いちばん多くOriHimeを導入してくださっています。 女性社員が産休、育休で数年間休んだ後、職場復帰がしづらくて辞めてしまうケースが多かったのですが、OriHimeを使って家に居ながら1時間でも2時間でも「出社」することで、同僚と関係性が維持できて、「仕事をしている」という実感が得られるのです。現時点で66台導入してくださっています。 国会議員の平将明さんもOriHimeで国会に出てみようと言ってくださっています。OriHimeを肢体不自由者だけが使うものではなく、誰もが使えるインフラにしてしまえばいいのです。国会議員が使っていたら、学校で使えない理由なんてありませんよね。 これまでは万能人材社会でした。日本だと政治家にも車椅子の人はなかなかいません。身体が不自由な人は上に立てなかった。でも、実際にはとても優秀でキャリアもある人材が、ある日ALSを発症してしゃべれなくなり、それで就職できなくなってしまっているケースも多くあります。 オリィ研究所のもうひとつの商品、「OriHime eye」は、視線移動だけで文字入力はもちろん、Windows PCのすべての操作が可能になっています。定価45万円ですが、ALSや筋ジストロフィーの患者さんが購入補助を使えば4万5,000円で導入できます。 ビジネス経験のない自分がここまでやってこれたのは、メンターの存在がありました。メリルリンチ証券の元会長の藤沢さんという方で、ALSを発症して10年間寝たきりだったところ、初期段階のOriHime eyeを購入してくださったユーザーさんです。残念ながら亡くなってしまいましたが、最後の瞬間までオリィ研究所の顧問を務めてくださいました。エンジェル投資家でもありました。 がんも患っていらっしゃったのに「20代の若者とベンチャーができるなんて楽しい」とずっと言ってくださった。私も、将来寝たきりになったとしても、若者たちとプロジェクトをやりたいです。それが藤沢さんの生き様から学んだことです。
 吉藤:2018年、肉体労働が可能な大型の「OriHime-D」を開発しました。生前の番田と話していたとき「お客さんがオフィスに来て、会議室に案内するのも私、番田の名刺交換するのもお茶を出すのも私なのはおかしくないか」と言ったら「じゃあ、そのための身体をつくってくれ」とリクエストされたことがきっかけです。ALS患者さんが、OriHime-Dを使って熱いコーヒーを私に手渡すことに成功しました。そこで思いついたのがカフェです。 2018年11月に発表し、10日間限定でオープンした「分身ロボットカフェDAWN」は、日本財団さん、ANAさんとのパートナーシップで実現し、当時の野田総務大臣と一緒にOriHime-Dがテープカットに参加しています。メディアにも96社ほど来て頂き、働きたいという患者さんから100名の応募が来ました。 参考リンク:"分身ロボット"でカフェ店員に(NHKニュース) 働きたいと思っている肢体障害者はたくさんいるのに、働き方がわからない。雇いたいと思っている企業もたくさんあるのに、どうやって働いてもらっていいのかわからない。私はOriHimeを使った働き方を「ロボットテレワーク」と名付けました。これが広まれば、どんなひとでも自分の意思で自分の行きたいところに行って、会いたい人に会える。そしてなにより、死ぬ瞬間まで誰かに必要とされる。 分身ロボットカフェは今年も開催が決まり、スポンサーを募集しているところです。カフェ以外にもこれから紹介がある宇宙プロジェクトなど、私たちと共に取り組んでくださるパートナー企業様がいらっしゃったら、ぜひお声がけください。
吉藤:2018年、肉体労働が可能な大型の「OriHime-D」を開発しました。生前の番田と話していたとき「お客さんがオフィスに来て、会議室に案内するのも私、番田の名刺交換するのもお茶を出すのも私なのはおかしくないか」と言ったら「じゃあ、そのための身体をつくってくれ」とリクエストされたことがきっかけです。ALS患者さんが、OriHime-Dを使って熱いコーヒーを私に手渡すことに成功しました。そこで思いついたのがカフェです。 2018年11月に発表し、10日間限定でオープンした「分身ロボットカフェDAWN」は、日本財団さん、ANAさんとのパートナーシップで実現し、当時の野田総務大臣と一緒にOriHime-Dがテープカットに参加しています。メディアにも96社ほど来て頂き、働きたいという患者さんから100名の応募が来ました。 参考リンク:"分身ロボット"でカフェ店員に(NHKニュース) 働きたいと思っている肢体障害者はたくさんいるのに、働き方がわからない。雇いたいと思っている企業もたくさんあるのに、どうやって働いてもらっていいのかわからない。私はOriHimeを使った働き方を「ロボットテレワーク」と名付けました。これが広まれば、どんなひとでも自分の意思で自分の行きたいところに行って、会いたい人に会える。そしてなにより、死ぬ瞬間まで誰かに必要とされる。 分身ロボットカフェは今年も開催が決まり、スポンサーを募集しているところです。カフェ以外にもこれから紹介がある宇宙プロジェクトなど、私たちと共に取り組んでくださるパートナー企業様がいらっしゃったら、ぜひお声がけください。
 一般社団法人SORAのかけはし代表理事の仲佐昭彦様 仲佐:私は普段は長野県の上田市にある医療機器メーカーで開発業務をしています。オリィさんとは4年前の医療系の学会で出会い、すっかりファンになってしまいました。そのとき私が「どうせならOriHimeで宇宙まで行ってしまおう」と発言したことがきっかけで始まったのが「オリヒメスペースフライトプロジェクト」です。 日本人として最初に月面に降り立つのが、病院の子供だったらおもしろいじゃないか、と思ったのです。言い出しっぺということで、仲間を集めて、一般社団法人SORAのかけはしを立ち上げました。 私も、昔は、本日出席されているとみなさんと同じような大企業で研究開発をしていました。その頃の自分は、社会のために何かをしたいなんて考えもせず、自分の見える世界だけで生きていました。それが、オリィさんとの出会いを通じて、初めて「ちょっと宇宙に行ってくる」と気軽に言える社会に変えてみたい、と思えたのです。 今では小型人工衛星の世界的権威である東大の中須賀真一教授をはじめ、心理学、小児医療の第一人者から、女子高生までが混在するチームができ、2018年の夏にJAXAの承認委員会も通過しています。 分身ロボットを宇宙に送る、という発想自体が、なかなか日本人以外には思いつけないと私は思います。また、このプロジェクトを通じてALSを始めとする病気のことを多くの人に知っていただくことが、治療の進歩や患者のQOL向上にも貢献するはずです。 立場を超えて、世代を超えて、チームジャパンの一員として参加してくださるパートナーさんがいらっしゃったら、ぜひ応援していただければと思います。
一般社団法人SORAのかけはし代表理事の仲佐昭彦様 仲佐:私は普段は長野県の上田市にある医療機器メーカーで開発業務をしています。オリィさんとは4年前の医療系の学会で出会い、すっかりファンになってしまいました。そのとき私が「どうせならOriHimeで宇宙まで行ってしまおう」と発言したことがきっかけで始まったのが「オリヒメスペースフライトプロジェクト」です。 日本人として最初に月面に降り立つのが、病院の子供だったらおもしろいじゃないか、と思ったのです。言い出しっぺということで、仲間を集めて、一般社団法人SORAのかけはしを立ち上げました。 私も、昔は、本日出席されているとみなさんと同じような大企業で研究開発をしていました。その頃の自分は、社会のために何かをしたいなんて考えもせず、自分の見える世界だけで生きていました。それが、オリィさんとの出会いを通じて、初めて「ちょっと宇宙に行ってくる」と気軽に言える社会に変えてみたい、と思えたのです。 今では小型人工衛星の世界的権威である東大の中須賀真一教授をはじめ、心理学、小児医療の第一人者から、女子高生までが混在するチームができ、2018年の夏にJAXAの承認委員会も通過しています。 分身ロボットを宇宙に送る、という発想自体が、なかなか日本人以外には思いつけないと私は思います。また、このプロジェクトを通じてALSを始めとする病気のことを多くの人に知っていただくことが、治療の進歩や患者のQOL向上にも貢献するはずです。 立場を超えて、世代を超えて、チームジャパンの一員として参加してくださるパートナーさんがいらっしゃったら、ぜひ応援していただければと思います。
 OriHimeを使ったワークショップの模様 参加者:DBICメンバー企業には保険会社も複数居ます。医療保険の商品として、子供が長期入院した場合は分身ロボットをレンタルできるオプションをつけ、リモートで通学するサービスがあったらいいのではと考えましたが、実現にあたって何かハードルはありますか? 吉藤:ハードルはほとんどないかなと思います。そういったサービスは可能です。私が特に重要だと思うのは「移動」と「出会い」と「役割を得る」という点です。ましてや肢体障害者の場合、今の日本では役割を得にくいでしょう。 ですから、今までの医療保険にある「お金」とか「設備」といった保障ではなく、「役割」を得られるという新しい保険が、テクノロジーとの組み合わせで開発できるのではないかと考えています。
OriHimeを使ったワークショップの模様 参加者:DBICメンバー企業には保険会社も複数居ます。医療保険の商品として、子供が長期入院した場合は分身ロボットをレンタルできるオプションをつけ、リモートで通学するサービスがあったらいいのではと考えましたが、実現にあたって何かハードルはありますか? 吉藤:ハードルはほとんどないかなと思います。そういったサービスは可能です。私が特に重要だと思うのは「移動」と「出会い」と「役割を得る」という点です。ましてや肢体障害者の場合、今の日本では役割を得にくいでしょう。 ですから、今までの医療保険にある「お金」とか「設備」といった保障ではなく、「役割」を得られるという新しい保険が、テクノロジーとの組み合わせで開発できるのではないかと考えています。  OriHimeを使ったワークショップの模様 参加者:番田さんから最初にメールを受け取って、どこが響いて、会おうと思ったのですか? 吉藤:今もし番田からメールが来ても、そんなに刺さらなかったかもしれません。その意味ではタイミングがよかったのもあります。当時、私はただの大学生で、つくったものを実験できる機会がなかった。実際に使ってくれる人を探すのが難しかったのです。そんなタイミングで、あのとき番田が、まだメディアにも出てなかった自分をよく見つけてくれたと思います。 そして、彼ほど「どうやったら自分が生きた証を残せるか」という思いが強い人もいませんでした。20年間寝たきりで学校にも行っていない、顎を使って文章は打てるけどビジネスメールなんて打てない、改行もしていない長文が送られてきて、最初は「うわ」と思いましたよ。でも、OriHimeというロボットを使って、同じ病院で亡くなっていった子どもたちのためになにかしたい、という強いメッセージに心を打たれました。 当たり前に学校に行ける人は「いかに学校をさぼるか」を考えますよね。それとは逆で、私は研究が好きすぎて休みたくない。番田も同じで「今まで十分休んだ」と。何もしないことの辛さを知っているが故に、なにかしたくてたまらないのです。 今年も分身ロボットカフェを開催すると予告したら、100人以上応募があって、半数くらいの面接を終えたのですが、皆さんすごい熱意です。そういう人にちゃんと仕事を割り振れば、彼らは成長できるし、企業にとっても労働力になると私は確信しています。だからこそ、こういう方々が社会で働けるようにしたい。それこそ番田が望んだことです。
OriHimeを使ったワークショップの模様 参加者:番田さんから最初にメールを受け取って、どこが響いて、会おうと思ったのですか? 吉藤:今もし番田からメールが来ても、そんなに刺さらなかったかもしれません。その意味ではタイミングがよかったのもあります。当時、私はただの大学生で、つくったものを実験できる機会がなかった。実際に使ってくれる人を探すのが難しかったのです。そんなタイミングで、あのとき番田が、まだメディアにも出てなかった自分をよく見つけてくれたと思います。 そして、彼ほど「どうやったら自分が生きた証を残せるか」という思いが強い人もいませんでした。20年間寝たきりで学校にも行っていない、顎を使って文章は打てるけどビジネスメールなんて打てない、改行もしていない長文が送られてきて、最初は「うわ」と思いましたよ。でも、OriHimeというロボットを使って、同じ病院で亡くなっていった子どもたちのためになにかしたい、という強いメッセージに心を打たれました。 当たり前に学校に行ける人は「いかに学校をさぼるか」を考えますよね。それとは逆で、私は研究が好きすぎて休みたくない。番田も同じで「今まで十分休んだ」と。何もしないことの辛さを知っているが故に、なにかしたくてたまらないのです。 今年も分身ロボットカフェを開催すると予告したら、100人以上応募があって、半数くらいの面接を終えたのですが、皆さんすごい熱意です。そういう人にちゃんと仕事を割り振れば、彼らは成長できるし、企業にとっても労働力になると私は確信しています。だからこそ、こういう方々が社会で働けるようにしたい。それこそ番田が望んだことです。  OriHimeを使ったワークショップの模様 参加者:企業側は「障害者を雇用したいけれど、どういう役割を与えたらいいのかわからない」というのが共通の悩みだと感じています。一般の事業会社として、どういう役割を与えるのが双方にとって効果的でしょうか? 吉藤:その部分は、今、まさに様々な企業様と検証をさせていただいているところです。現時点で、これが役に立つ、としてわかりやすいのが受付業務です。通訳ができる人なら通訳もあります。 そしてスケジュール管理含めた秘書業務。社長なら常に秘書がいるかもしれませんが、一般の営業マンの場合はスケジュールの空き時間を相手に教えるだけでも難しいことがよくありますよね。ひとつのチーム5人くらいにつき、遠隔ロボットが毎日テーブルにいるだけで、状況や忙しさをわかった上で、スケジュールを入れてくれるようになります。しかも口頭でもミーティングできる。実際に番田がやっていたのがこの業務ですが、めちゃくちゃ助かります。 オリィ研究所から人材の紹介もできます。分身ロボットカフェをやったことによって、働きたい肢体障害者がたくさんいることが伝わり、企業としても、寝たきりや病院の中だと雇い方がわからなかったけれど、この方法なら普通の人間と同じに雇いたいという声が増えました。会社としても人材紹介の免許も取りました。 今までは、とにかく身体を動かすことができるのが優先で、知的障害の人が採用されていました。でも、物理的に身体を運べない重度肢体障害者がロボットで働けることがわかったのです。法定雇用率を満たすために誰でもできる作業をしてもらう、というのも実際には必要かもしれませんが、業務として役立っていて、自分のがんばりが会社の成長につながっている、と実感できることを目指したいです。 私達から人材は紹介できますし、いろいろな提案もできます。ぜひご依頼ください。
OriHimeを使ったワークショップの模様 参加者:企業側は「障害者を雇用したいけれど、どういう役割を与えたらいいのかわからない」というのが共通の悩みだと感じています。一般の事業会社として、どういう役割を与えるのが双方にとって効果的でしょうか? 吉藤:その部分は、今、まさに様々な企業様と検証をさせていただいているところです。現時点で、これが役に立つ、としてわかりやすいのが受付業務です。通訳ができる人なら通訳もあります。 そしてスケジュール管理含めた秘書業務。社長なら常に秘書がいるかもしれませんが、一般の営業マンの場合はスケジュールの空き時間を相手に教えるだけでも難しいことがよくありますよね。ひとつのチーム5人くらいにつき、遠隔ロボットが毎日テーブルにいるだけで、状況や忙しさをわかった上で、スケジュールを入れてくれるようになります。しかも口頭でもミーティングできる。実際に番田がやっていたのがこの業務ですが、めちゃくちゃ助かります。 オリィ研究所から人材の紹介もできます。分身ロボットカフェをやったことによって、働きたい肢体障害者がたくさんいることが伝わり、企業としても、寝たきりや病院の中だと雇い方がわからなかったけれど、この方法なら普通の人間と同じに雇いたいという声が増えました。会社としても人材紹介の免許も取りました。 今までは、とにかく身体を動かすことができるのが優先で、知的障害の人が採用されていました。でも、物理的に身体を運べない重度肢体障害者がロボットで働けることがわかったのです。法定雇用率を満たすために誰でもできる作業をしてもらう、というのも実際には必要かもしれませんが、業務として役立っていて、自分のがんばりが会社の成長につながっている、と実感できることを目指したいです。 私達から人材は紹介できますし、いろいろな提案もできます。ぜひご依頼ください。  OriHimeを使ったワークショップの模様 参加者:テレワークは働いている感じがしないと言われます。やりがいや帰属意識は、どういうことから芽生えていくのでしょうか? 吉藤:その点については諸説あリますので、あくまで私の経験からのひとつの答えになります。 番田のケースでわかったことですが、顧客なのか、プライベートの来客なのか別にして、接客はわかりやすいです。分身ロボットカフェの良さも、対人であるという点でした。喜んでくれる人が目の前にいると、モチベーションとが湧きやすいです。 喜んでくれるのが上司であったり、いろいろなパターンがあると思いますが、とにかく相手が人であり、コミュニケーションがあり、自分が話すべき内容があり、リアクションを返してくれることが重要です。リアクションこそコミュニケーションの本質であるというのが私の考えです。 例えばテレワークで指示を受けて家で資料をつくったとしても、それがマルなのかバツなのか、場合によってはそれすらなく、つくった資料はこれであっているのか、このままでいいのか、と思っていても、現場の空気感がわからない。 人間は人工知能に褒められたいのではなく、同じ人間に笑顔になってもらうというところに、強いモチベーションを感じるのです。私は多くの末期がん患者、ALSの方々とお会いしていますが、ほとんどの方が延命するか死ぬかを選ぶときに仰るのは「生きるとは、誰かの役に立つことである」という内容のことです。 社会人であれば、会社の成長とか、家庭とか、いろいろ目標設定があると思いますが、最後は人は結局そこに行き着くのではないでしょうか。誰かを笑わせるとか些細な事も含めて、コミュニケーションこそが人を生かし続けられます。だれかとなにかを一緒にできる自由、それは権利だと私は思っています。そこにフォーカスした開発をこれからも続けたいです。
OriHimeを使ったワークショップの模様 参加者:テレワークは働いている感じがしないと言われます。やりがいや帰属意識は、どういうことから芽生えていくのでしょうか? 吉藤:その点については諸説あリますので、あくまで私の経験からのひとつの答えになります。 番田のケースでわかったことですが、顧客なのか、プライベートの来客なのか別にして、接客はわかりやすいです。分身ロボットカフェの良さも、対人であるという点でした。喜んでくれる人が目の前にいると、モチベーションとが湧きやすいです。 喜んでくれるのが上司であったり、いろいろなパターンがあると思いますが、とにかく相手が人であり、コミュニケーションがあり、自分が話すべき内容があり、リアクションを返してくれることが重要です。リアクションこそコミュニケーションの本質であるというのが私の考えです。 例えばテレワークで指示を受けて家で資料をつくったとしても、それがマルなのかバツなのか、場合によってはそれすらなく、つくった資料はこれであっているのか、このままでいいのか、と思っていても、現場の空気感がわからない。 人間は人工知能に褒められたいのではなく、同じ人間に笑顔になってもらうというところに、強いモチベーションを感じるのです。私は多くの末期がん患者、ALSの方々とお会いしていますが、ほとんどの方が延命するか死ぬかを選ぶときに仰るのは「生きるとは、誰かの役に立つことである」という内容のことです。 社会人であれば、会社の成長とか、家庭とか、いろいろ目標設定があると思いますが、最後は人は結局そこに行き着くのではないでしょうか。誰かを笑わせるとか些細な事も含めて、コミュニケーションこそが人を生かし続けられます。だれかとなにかを一緒にできる自由、それは権利だと私は思っています。そこにフォーカスした開発をこれからも続けたいです。  OriHimeを使ったワークショップの模様
OriHimeを使ったワークショップの模様
他のDBIC活動
他のDBICコラム
他のDBICケーススタディ

【レポート】企業変革実践シリーズ第37回 日本舞踊家・有馬和歌子氏に学ぶ、感性とテクノロジーが拓く企業変革

【レポート】2025年12月 DBICアップデート

【レポート】自分の「感覚」に再び出会う旅。DBIC デジタル・ストーリーテリング(DST)ワークショップを開催

【レポート】UNLOCK QUEST2025上期レポート 問いを立てて行動し続けること
一覧へ戻る
一覧へ戻る
一覧へ戻る

